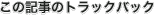エゾを出発して苦節10年目にして念願の沖縄移住を果たした道産子のひとり言です。。。沖縄生活も3年を超えました~!!
ステーショナリー・デジモノが大好きで、「送料別途」地域という逆境を撥ね除け日々物欲(通販)に邁進してます(^_^;)
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新記事
(05/18)
(05/17)
(05/13)
(05/13)
(05/12)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
ikapoppo
性別:
非公開
自己紹介:
ikapoppoを名乗っておりますとおり、体は生きのいいイカの如くスケルトンでございます。
2002年頃 沖縄病発病
2004年頃 沖縄病が末期症状
となり、余命宣告を
受ける。
2006年 内地で治療を続ける
が効果が見られず、
入院(移住)しか治
療方針がないと宣
告される。
2月 内地での治療と平行
して入院先(棲家)を
探しを始める。
10月 内地での治療を
諦め入院(移住)
現在 島ナイチャ~生活を満喫!
好きなモノ:カネ、独り引きこもる時間、文具、カメラ、パソコン、機械モノ全般、ネット通販、レザークラフト、DIY、アメリカドラマ、原付、時代劇、放浪、所ジョージ的生き方、カネ
キライなモノ:仕事、団体行動、ボランティア、ギャァギャァ騒ぐコドモ、主婦の愚痴、博愛精神、義理の飲み会
2002年頃 沖縄病発病
2004年頃 沖縄病が末期症状
となり、余命宣告を
受ける。
2006年 内地で治療を続ける
が効果が見られず、
入院(移住)しか治
療方針がないと宣
告される。
2月 内地での治療と平行
して入院先(棲家)を
探しを始める。
10月 内地での治療を
諦め入院(移住)
現在 島ナイチャ~生活を満喫!
好きなモノ:カネ、独り引きこもる時間、文具、カメラ、パソコン、機械モノ全般、ネット通販、レザークラフト、DIY、アメリカドラマ、原付、時代劇、放浪、所ジョージ的生き方、カネ
キライなモノ:仕事、団体行動、ボランティア、ギャァギャァ騒ぐコドモ、主婦の愚痴、博愛精神、義理の飲み会
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
アクセス解析
03
名古屋の方スイマセン
けっして名古屋という土地がイヤと言っているのではないので大目に見てやってください
私がよく仕事上使う地名の中に「名古屋」が含まれるのですが、漢字で3文字なんですよねー
これまたよく使う地名「大阪」や「東京」、「沖縄」はひらかなにすると名古屋よりも文字数は多いですが、漢字では2文字
変なところだけA型な私は、箇条書きで書く時に、名古屋だけ出っ張ってしまうのがすごいイヤなんです
例えば・・・
みたくWORDやメールなどで箇条書きにして書くことがよくあるのですが、一文字分の出っ張りがすごいイヤです
余裕がある時は
と出っ張りの一文字分スペースを入れるのですが、「・・・」はまたビミョーで1.5角なんです
フツーにスペースキーを1回押すと
となってしまうんですよ
そういう些細な事が気になってしまうやっかいなA型です
前に印刷・出版業界にいたので、ちょっとした文字の揺れが気になるのもあると思います
地名って漢字二文字のモノがフツーだと思いません?
それはなぜかって言うと、偶然ではないんです!
これより先はEin Geschichtsmeister(ドイツ語です)のウンチクなので読んでやってもイイという心の広い方は読んでやってください
けっして名古屋という土地がイヤと言っているのではないので大目に見てやってください

私がよく仕事上使う地名の中に「名古屋」が含まれるのですが、漢字で3文字なんですよねー

これまたよく使う地名「大阪」や「東京」、「沖縄」はひらかなにすると名古屋よりも文字数は多いですが、漢字では2文字
変なところだけA型な私は、箇条書きで書く時に、名古屋だけ出っ張ってしまうのがすごいイヤなんです

例えば・・・
東京・・・
大阪・・・
名古屋・・・
沖縄・・・
みたくWORDやメールなどで箇条書きにして書くことがよくあるのですが、一文字分の出っ張りがすごいイヤです
余裕がある時は
東京 ・・・
大阪 ・・・
名古屋・・・
沖縄 ・・・
と出っ張りの一文字分スペースを入れるのですが、「・・・」はまたビミョーで1.5角なんです

フツーにスペースキーを1回押すと
東京 ・・・
大阪 ・・・
名古屋・・・
沖縄 ・・・
となってしまうんですよ
そういう些細な事が気になってしまうやっかいなA型です

前に印刷・出版業界にいたので、ちょっとした文字の揺れが気になるのもあると思います
地名って漢字二文字のモノがフツーだと思いません?
それはなぜかって言うと、偶然ではないんです!
これより先はEin Geschichtsmeister(ドイツ語です)のウンチクなので読んでやってもイイという心の広い方は読んでやってください

日本の地名や名字は漢字二文字が多いのには理由があります
まず、名字ですが、これは地名が由来であることが多いので、地名が漢字二文字だと必然的に名字も漢字二文字が多いことになります
それではなぜ地名は漢字二文字が多いのかという本題ですが、一言でいえば日本の古代において、お国が「地名は漢字二文字でつけろ!」と命令を出したからです
具体的には「続日本紀」の和銅六年(西暦713年)五月の条に「風土記」を作れ!という命令があったとあり、その指示の中に「畿内七道諸国郡郷名著好字」という記事があります
「畿内七道諸国郡郷名著好字」を簡単に訳すと「畿内七道( 畿内・東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道)の諸国の国名、郡名、郷名にはめでたい名をつけ、美しい文字で著せ」といった内容です
この指示の内容には二字で表記しろといったことも含まれていたようです
事実風土記ではほぼ漢字二文字で地名が表記されています
お次に「延喜式」(康保四年(967年)施行)で「凡諸国部内郡里等名、並用二字、必取嘉名」とあり、この時点ではっきりと漢字二文字で地名を表記しろと当時の法律で規定されました
例えば現在でも大阪にある「和泉」という地名は「泉」と一文字で表記でき、おそらく由来も水に関係あるのでしょうが、上記の法律にひっかかるので「和泉」と表記されるようになりました
各地にある「那珂」という地名も元々は「中」の一文字で表されていた地名を「那珂」としたのでしょう
わかりやすい地域で「加美」「那珂」「志茂」といった地名が並んでいるところがありますが、この地名の由来は漢字からでは推測は不可能ですが、音で「かみ」「なか」「しも」として考えたら想像がつきます
おそらくその地域に川が流れていて、上流から下流に向かって「加美」「那珂」「志茂」と並んでいるか、北が「加美」で南が「志茂」と並んでいるハズです
奈良時代以前は「上」「中」「下」だった地名を無理やり漢字二文字で表記した結果、本来の意味がわからなくなってしまっています
沖縄には「真栄田」という地名がありますが、古代の法則に則ると「前田」となってしまうわけです
千年以上前の法令が現代まで残っているワケがない!といわれるかもしれませんが、根源は奈良時代にあります
一文字や三文字の地名って地名的には新しいハズです
まぁとりあえずそんなところです
以上ikapoppoのウンチクでした
まず、名字ですが、これは地名が由来であることが多いので、地名が漢字二文字だと必然的に名字も漢字二文字が多いことになります
それではなぜ地名は漢字二文字が多いのかという本題ですが、一言でいえば日本の古代において、お国が「地名は漢字二文字でつけろ!」と命令を出したからです
具体的には「続日本紀」の和銅六年(西暦713年)五月の条に「風土記」を作れ!という命令があったとあり、その指示の中に「畿内七道諸国郡郷名著好字」という記事があります
「畿内七道諸国郡郷名著好字」を簡単に訳すと「畿内七道( 畿内・東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道)の諸国の国名、郡名、郷名にはめでたい名をつけ、美しい文字で著せ」といった内容です
この指示の内容には二字で表記しろといったことも含まれていたようです
事実風土記ではほぼ漢字二文字で地名が表記されています
お次に「延喜式」(康保四年(967年)施行)で「凡諸国部内郡里等名、並用二字、必取嘉名」とあり、この時点ではっきりと漢字二文字で地名を表記しろと当時の法律で規定されました
例えば現在でも大阪にある「和泉」という地名は「泉」と一文字で表記でき、おそらく由来も水に関係あるのでしょうが、上記の法律にひっかかるので「和泉」と表記されるようになりました
各地にある「那珂」という地名も元々は「中」の一文字で表されていた地名を「那珂」としたのでしょう
わかりやすい地域で「加美」「那珂」「志茂」といった地名が並んでいるところがありますが、この地名の由来は漢字からでは推測は不可能ですが、音で「かみ」「なか」「しも」として考えたら想像がつきます
おそらくその地域に川が流れていて、上流から下流に向かって「加美」「那珂」「志茂」と並んでいるか、北が「加美」で南が「志茂」と並んでいるハズです
奈良時代以前は「上」「中」「下」だった地名を無理やり漢字二文字で表記した結果、本来の意味がわからなくなってしまっています
沖縄には「真栄田」という地名がありますが、古代の法則に則ると「前田」となってしまうわけです
千年以上前の法令が現代まで残っているワケがない!といわれるかもしれませんが、根源は奈良時代にあります
一文字や三文字の地名って地名的には新しいハズです
まぁとりあえずそんなところです
以上ikapoppoのウンチクでした

PR
無題
>例えば現在でも大阪にある「和泉」という地名は「泉」と一文字で表記でき、おそらく由来も水に関係あるのでしょうが、上記の法律にひっかかるので「和泉」と表記されるようになりました
へぇ~×10
そうなんだ。知らなかった。確かに読みから一文字表記できるじゃんって
思った覚えあるわ。
ところで、これ↓
>余裕がある時は
・・・
>と出っ張りの一文字分スペースを入れるのですが、「・・・」はまたビミョーで1.5角なんです
わかる!!俺もやる!!(笑)
微妙に1.5画でスペースとかで思うように整えられないとき、すごくむかつく!
この辺A型なんだなぁ、、、俺も。しかし、普段はA型には見られないんだけ
どなぁ。(なぜかO型でしょって言われる。まぁ、母親がO型だけれどもw)
へぇ~×10
そうなんだ。知らなかった。確かに読みから一文字表記できるじゃんって
思った覚えあるわ。
ところで、これ↓
>余裕がある時は
・・・
>と出っ張りの一文字分スペースを入れるのですが、「・・・」はまたビミョーで1.5角なんです
わかる!!俺もやる!!(笑)
微妙に1.5画でスペースとかで思うように整えられないとき、すごくむかつく!
この辺A型なんだなぁ、、、俺も。しかし、普段はA型には見られないんだけ
どなぁ。(なぜかO型でしょって言われる。まぁ、母親がO型だけれどもw)
かずさん / 2008/03/03(Mon) /
無題
なぜか俺はA型と言って納得してもらえた事は一度も
ありません(笑)。
むしろ逆に、
『絶対、A型じゃないから。調べなおしてみたら?』
とまで言われた事があるよ(^^;
ありません(笑)。
むしろ逆に、
『絶対、A型じゃないから。調べなおしてみたら?』
とまで言われた事があるよ(^^;
かずさん / 2008/03/03(Mon) /